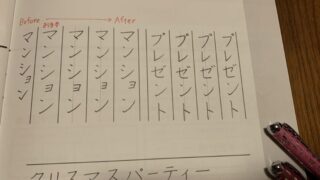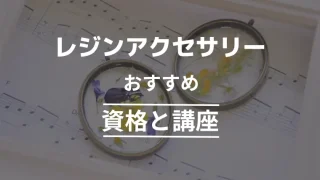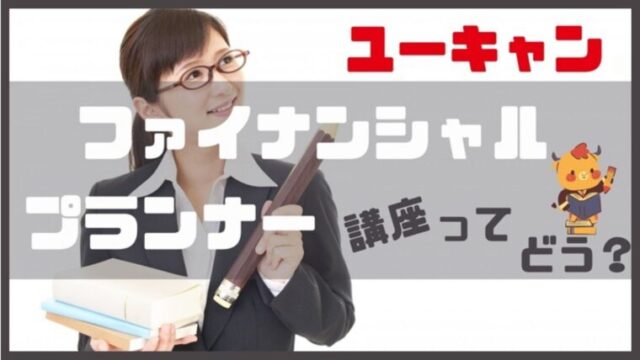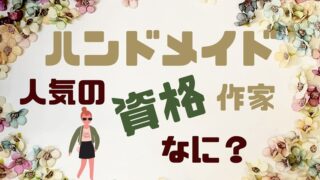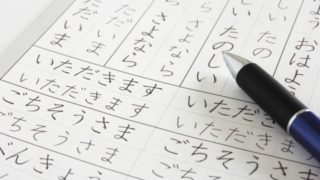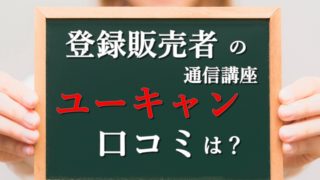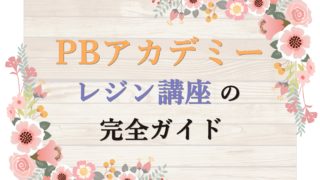着物は着付け師に着せ付けてもらうのが一般的になっています。
着付けには国家資格から民間資格まで多くの資格があります。
着付け師として活躍するには、資格は必須と考えておきましょう。
この記事では着付け師として持っておきたい資格を6つご紹介し、それらの特徴やメリットと取得法まで解説いたします。
筆者は、着付けを装道礼法きもの学院で習い、在学中にきものコンサルタント9級を取得しました。
着付け師に資格は必要か

着付け師として活躍するには、資格を持っていないとなれないのか、気になりますよね。
この疑問にズバリ答えます!
着付け師を仕事にするならば、資格取得は必須と考えておきましょう。
これは実際に現場を見てきた私個人の意見ですが、資格は持っていた方が身のためです。
正確に言うと資格がなくても活動自体はできます。
例えば自動車は免許がないと運転できませんが、着付けにはそういった決まりはないからです。
ですが、やはり着付け師の資格を持っていると自分のアピールポイントにもなりますし、何よりお客様から得られる信頼がけた違いに大きくなります。
また、お給料面でも差が出てきますので、取得した方が良いのは明らかです。
あなたが着付けをしてもらおうと思った時、資格を持った着付け師が担当だと、なんとなく安心しませんか?
ですので、着付け師の資格は積極的に取得しましょう!
着付け師に必要な資格の種類

それではここから、着付け師の資格について説明していきます。
着付け師の資格は、ほとんどが着付け教室で取得するスタイルになっています。
実は着付け師の資格は多数存在しているのですが、今回は私がこれだ、と思うものを6種類ピックアップします。
着付け技能検定
全日本着付け技能センターが運営する技能検定です。
厚生労働省の指定を受けている、着付け師資格の国家資格です。
着付けを勉強しているのであれば、一度は耳にしたことがあるかもしれませんね。
抜群の知名度がありますので、どこの場に行っても着付け師の資格として通用することが最大のメリットと言えます。
着付け教室等で見られる流派がないため、どの教室、団体に所属しても受験できます。
そのため、受験するには個人で申し込むか着付け技能検定を対策している教室に通うのが一般的な流れになっています。
なお、この資格は既に着付け師として活躍している経験者向けとなっています。
実務経験等一定の条件を満たさなければ受験資格が与えられないため、受験するには注意が必要です。
では、以下簡潔にまとめましたのでご覧ください。
1級着付け技能士
- 受験資格 実務経験5年以上
- 2級着付け技能士に合格していること
- 着装の他に筆記試験もあり
- 受験費用は学科試験8,900円、実技試験18,500円
2級から順を追って受験しましょう。
いきなり1級を受験することはできないので、注意してください。
2級着付け技能士
- 受験資格 実務経験2年以上
- 着装の他に筆記試験もあり
- 受験費用は学科試験8,900円、実技試験16,700円
着付師
大手着付け教室である長沼静きもの学院で取得できる民間資格です。
上記紹介した国家資格とは違い、着付け教室が運営している資格。
着付師の資格を取得するには、着付師育成科に通うことです。
1年間で3級、2級、1級と順を追って資格を取得できますよ。
最短3ヶ月で着付師の資格を取ることができます。
1日も早く着付け師になりたいと考えるあなたにはうってつけですね。
資格取得後には「シザブルスタッフ」という学院独自の人材登録システムに登録することができます。
式場や美容室など色々なクライアントと提携しているので、活躍の場があるのが嬉しいポイントですね。
きものコンサルタント
着付け教室である装道礼法きもの学院で取得することができる資格です。
内閣府認定を受けている、国家資格に次ぐ公的資格となっています。
資格を取得するには、きものプロ養成コースに通いましょう。
終了後にはきものコンサルタント9級の資格が与えられます。
こちらは資格取得までに時間がかかるカリキュラムなのが注意ポイント。
着付けだけでなく、着物に関する知識も得ながらじっくり学びたいあなたにおススメの資格です。
きものコンサルタント1級を取得するには、きものプロ養成コース修了後更に上のクラスに通う必要があります。
取得までにかなり根気が要る資格となっています。
花嫁着付師認定証
ハクビ花嫁着付専門学院で取得できる民間資格です。
ブライダルに特化した資格であることが大きな特徴となっています。
専門学院とありますが、学校ではなくあくまでも着付け教室なので、どなたでもレッスンできます。
コースは基礎科1つのみで、半年から1年かけて技術を身につけます。
花嫁の着付けはもちろん、メイク、かつらと花嫁着付けをトータルで学ぶことができるので、ブライダル業界を目指しているあなた向けの資格と言えます。
近年は和装で結婚式を挙げるカップルも多いので、需要もどんどん増えていく着付け資格の1つです。
着物着付指導士
全日本和装コンサルタント協会が運営する資格です。
厚生労働省が指定しているため、こちらも着付け技能検定と同様の国家資格です。
また、他の資格と異なり、ひとつ大きな特徴があります。
それは、プロのための資格であるということです。
簡単に説明すると、着付けを教える立場にある講師のための資格なのです。
そのため受験資格は全日本和装コンサルタント協会の会員であること、もしくは着付け教室の運営者や講師であることが条件になっています。
資格取得するには、全日本和装コンサルタント協会に所属している着付け教室に通うのが一番分かりやすいのでおススメです。(対策や規定等伝授してもらえるので)
着物着付指導士3級から1級まで受験できるようになっており、1級の実技試験はなんと十二単の着装となっています!
難易度がかなり高いことがうかがえますね。
将来着付け教室を開きたいと考えているのであれば、この資格も視野に入れておくと良いでしょう。
きもの文化検定
全日本きもの振興会が運営する検定試験です。
こちらは着付けというより、着物そのものの知識を深める資格になっています。
直接着付けとは関係ありませんが、着付け師として活躍するには着物に関するあらゆる知識を身につける必要があるので、あえて紹介します。
5級から1級まで設けており、5級、4級、3級は併願して受験可能となっています。
ですので、知識がしっかり身につき自信があれば併願受験も有りですね!
受験するには、少し面倒ですが個人で申し込みをしましょう。
ホームページ上からインターネットで申し込むこともできるので、郵送の手間も省けて便利です。
なお、着付けの資格が取れる教室については「BrushUP学び」の着付け教室選びのコツ教えます!をご覧下さい。無料で資料請求もできます。
着付け師が資格取得するメリット

続いては資格取得のメリットについてお話ししましょう。
着付け師の資格を取得したらどんな良いことがあるのか、以下にまとめました。
- 自分の自信に繋がる
- お客様など、クライアントに信頼してもらいやすい
- 働き方が選べる(会社勤め着付け師からフリーの着付け師まで様々)
- お給料アップが見込める!(ある意味一番のメリットかも)
他にもたくさんあるのですが、私が日々実感している項目を中心に挙げてみました。
もちろん資格取得さえすれば安泰!という訳ではないので絶対的なことは言えないのですが、私は着付け師の資格を持っていたことで怖いぐらいにお仕事がスムーズに決まったことがあります。
良いことだらけとまではいきませんが、私は自分に価値がついたと思っています。
あなたも着付け師の資格を取得し、自分の希少価値をどんどんあげていきましょう!
着付け師の資格取得までの道のり

上記資格の種類でも少し触れましたが、着付け師の資格を取得するにはある程度の日数がかかります。
どの資格を取得するかにもよりますが、だいたい1年以上かかるものと思っておきましょう。
働きながらの勉強ですと、もう少し日数が上乗せされると思ってください。
とても大変な道のりなので、もしかしたら途中で挫折したり、そう思うこともあるかもしれません。
そんなときは、少しペースを落としましょう。
焦らず、自分のペースで進めたほうが結局は長続きすると思いませんか。
継続できないと、取れる資格も取れなくなってしまいますから。
せっかくですし、楽しみながら資格取得を目指しましょう。
なお、着付けのすべての知識は、以下の通信講座を利用すると効率よく学べますよ☟
- SARAスクールの着物資格取得講座
 ※着物の知識が身につき資格取得が目指せる
※着物の知識が身につき資格取得が目指せる
着付け師の資格まとめ

最後に、着付け師の資格についておさらいしましょう。
ここまで説明してきたことをまとめていきます。
- 着付け技能検定
- 着付師
- きものコンサルタント
- 花嫁着付師認定証
- 着物着付指導士
- きもの文化検定
着付け師の資格はこれだけでなく、他にもたくさんあります。
着付け教室などが運営する民間資格は規定がそれぞれ違うので、自分がこれだと思う資格を取得しましょう。
人気記事:着付け師が派遣で働く理由とメリットは?派遣会社選びのコツも解説